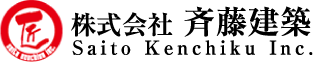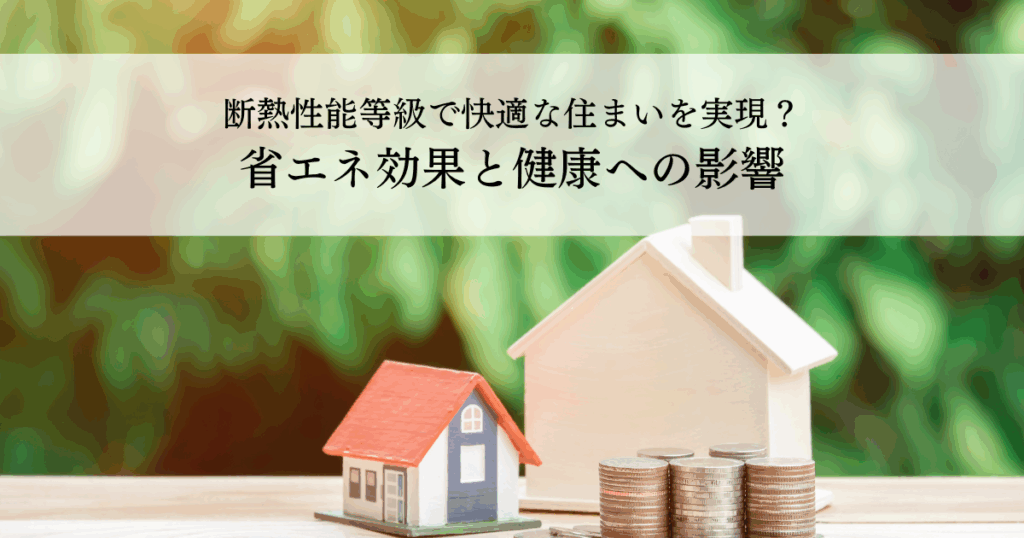快適な住まいづくりは、将来の豊かな暮らしを左右する重要な要素です。
特に、近年は地球温暖化による気候変動の影響が深刻化しており、住宅の省エネルギー化がますます重要になっています。
新築住宅を検討する際に、断熱性能は快適性や経済性、そして環境への配慮という観点から、見逃せないポイントと言えるでしょう。
そこで、今回は断熱性能等級と快適な住環境の関係について解説します。
断熱性能等級と省エネ効果
UA値・ηAC値の基礎知識
住宅の断熱性能を示す指標として、UA値とηAC値があります。
UA値は「外皮平均熱貫流率」を表し、住宅の外壁や窓などから熱が逃げ出すやすさを示します。
数値が小さいほど、断熱性能が高いことを意味します。
一方、ηAC値は「冷房期の平均日射熱取得率」で、太陽の日射熱がどれだけ室内に入り込むかを表します。
こちらも数値が小さいほど、遮熱性能が高いと言えます。
これらの値は、地域区分(日本の気候を8つの地域に分類)によって基準値が異なります。
等級ごとの省エネ性能比較
断熱等級は1~7の7段階で評価され、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。
等級4は、以前は最高等級でしたが、2025年以降は最低基準となります。
等級5はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準と同等、等級6と7はHEAT20という民間基準に準拠しており、それぞれ省エネ性能が向上します。
等級6は省エネ基準よりも約30%、等級7は約40%の暖冷房エネルギー消費量削減効果があるとされています。
光熱費削減効果の試算
断熱等級を上げることで、光熱費を削減できる効果が期待できます。
例えば、断熱等級4の住宅で年間24万円の光熱費がかかっていた場合、等級5にすると約20%削減され、年間約4.8万円の節約になります。
等級6、7ではさらに大きな削減効果が見込めます。
ただし、初期費用として断熱材などのコスト増加は考慮する必要があります。

断熱性能と快適な住環境
温度差による不快感の軽減
断熱性能が高い住宅では、室温が安定しやすいため、室温の大きな変化による不快感が軽減されます。
冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間を保ちやすくなり、特にヒートショックのリスクも低減できます。
ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が変動し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす危険性のある現象です。
結露対策と健康への影響
断熱性能が低いと、結露が発生しやすくなります。
結露はカビやダニの繁殖を招き、アレルギーや呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があります。
断熱性能を高めることで、結露を抑制し、健康的な住環境を確保できます。
夏冬の室温快適性向上
断熱性能が高い住宅は、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室温を保ちやすくなります。
エアコンの設定温度を控えめにしても快適に過ごせるため、省エネにも繋がります。
また、快適な室温は、睡眠の質の向上や、生活の質全般の向上にも貢献します。

まとめ
今回は、断熱性能等級と快適な住環境の関係について解説しました。
断熱等級を上げることで、省エネルギー効果による光熱費削減、温度差による不快感の軽減、結露対策による健康増進、そして夏冬の室温快適性向上といった様々なメリットが得られます。
2025年以降は断熱等級4が最低基準となるため、新築住宅を検討する際には、快適性と経済性、そして環境への配慮を考慮し、最適な断熱等級を選択することが重要です。
将来の住宅購入を検討する上で、断熱性能は重要な要素の一つであると理解いただけたかと思います。
快適な住まいを実現するためには、断熱性能についてしっかりと理解し、適切な選択をすることが大切です。